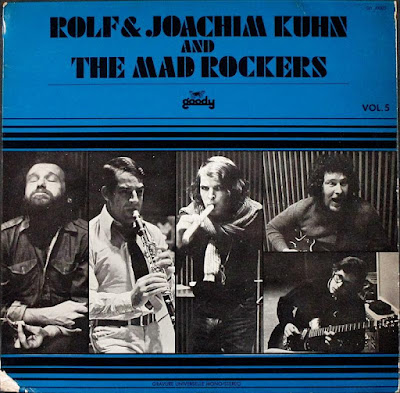まさに '過去の遺物' にして栄枯盛衰の象徴的アイテムでもある管楽器用マウスピース・ピックアップ。その端緒となった1960年代後半に登場する分厚いオクターヴで生成したオクターバーの歪みは、H&A Selmer Varitoneをきっかけに後続のC.G Conn Multi-Vider、GibsonのMaestro Sound System for WoodwindsからVox 'Ampliphonicシリーズ' のOctavoiceとStereo Multi-Voice、Gretsch Tone Divider、HammondからInnovex Condor RSMやAce Tone Multi-Vox EX-100といった国産品に至るまで、単音ソロの 'オクターヴ奏法' として重宝され、基本単音の管楽器における倍音生成に威力を発揮しました。
その元祖とも言うべき 'アタッチメント' というよりは、ひとつの大きなサウンド・システムと呼ぶに相応しいH&A SelmerのVaritone。1960年代後半のエフェクター開発においてアナログ時代に苦闘、試行錯誤していた効果がオクターバーであり、いわゆる単音入力に対して1、2オクターヴ下、または1オクターヴ上を付加することで分厚いトーンを生成します。例えばキーボードのような和音を単音楽器で電気的にシミュレートする場合は1970年代後半のデジタル以降、ピッチ・シフターが登場してからのこと。しかしこのオクターバーの開発においては、ギターより先に管楽器の 'アンプリファイ' の分野で製品化されたことはもっと特筆して良いと思いますね。
さて、'スイングジャーナル' 誌1968年10月号に寄稿された児山紀芳氏の記事 'エレクトリック・ジャズ - 可能性と問題点' では、当時の電気サックス・メーカーが付けたキャッチコピー '音楽にプッシュボタン時代来る' をテーマにして考察されております。面白いのはそもそもの開発の動機が当時のロックに象徴される 'エレキ革命' ではなく、ひとりで4つ同時に管を咥えて '四重奏' を披露するローランド・カークに触発されたというところです。以下抜粋。
- このところ、ジャズ界ではエレクトリック・サキソフォーンやエレクトリック・トランペットなど、新しく開発された電気楽器を使用するミュージシャンが増えてきましたが、ここではとくに貴方の領分である電気サックスの使用についてのご意見をきかせてほしい。
チャールズ・ロイド
"実は私もエレクトリック・サキソフォーンを最近手に入れたばかりだ。しかし、いまのところ私は、ステージで使ってみようとは思わない。少なくとも、現在の私のカルテットでは必要がない。というのも私自身、これまでのサキソフォーンにだってまだまだ可能性があると考えているからだ。それに、人が使っているからといって、流行だからといって、必要もないのに使うことはない。もし、将来電気サックスが自分の音楽にどうしても必要になれば、もちろん使うかもしれないが・・。"
スタン・ゲッツ
"元来、サキソフォーンという楽器は、他のいかなる楽器よりも人間の声をじかに伝達する性質がある。だから、サックスは肉体の一部となり、肉体とつながりをもってこそ、はじめて自分自身を正しく純粋に表現しうる楽器となる。その点、エレクトリック・サックスは、人間と楽器の中間に電気的な操作を介入させようというのだから、純粋性がなくなるし不自然だ。私は不自然なものは好まないし、世の中がいかに電化されたとしても、少なくとも私にとって電気サックスは無用だ。"
"このところエレクトリック・アルト・サックスをもっぱら使用しているリー・コニッツは、サックスが電化されたことにより、これまでの難問題が解決されたと語っている。コニッツが従来直面していた難問題とは、リズム・セクションと彼のアルト・サックスとの間に、いつも音量面で不均衡が生じていたことをさしている。つまりリズム・セクションの顔ぶれが変わるたびに、ソロイストであるコニッツはそのリズム・セクションのサウンドレベルに自己を適応させなければならなかったし、リズム・セクションのパワーがコニッツのソロを圧倒してしまう場合がよくあった。電化楽器ではサウンド・レベルを自由に調整することができるからこうした不均衡を即時に解消できるようになり、いまではどんなにソフトなリズム・セクションとも、どんなにヘヴィーなリズム・セクションとも容易にバランスのとれた演奏ができるという。しかも、リー・コニッツが使っている 'コーン・マルチ・ヴァイダー' は1本のサックスで同時に4オクターヴの幅のあるユニゾン・プレイができるから、利点はきわめて大きいという。先月号でも触れたように、コニッツは1967年9月に録音した 'The Lee Konitz Duets' (Milestone)のなかで、すでにエレクトリック・サックスによる演奏を吹き込んでいるが、全くの独奏で展開される 'アローン・トゥゲザー' で 'コーン・マルチ・ヴァイダー' の利点を見事に駆使している。この 'アローン・トゥゲザー' で彼は1オクターヴの音を同時に出して、ユニゾンでアドリブするが、もうひとつの演奏 'アルファニューメリック' ではエディ・ゴメス(ベース)やエルヴィン・ジョーンズ(ドラムス)、カール・ベルガー(ヴァイブ)、ジョー・ヘンダーソン(テナー・サックス)ら9人編成のアンサンブルで、エレクトリック・サックスを吹き、自分のソロをくっきりと浮き彫りにしている。ここでのコニッツは、アルト・サックスの音量面をアンプで増大するだけにとどめているがその効果は見逃せない。"
→Gretsch Tone Divider Model 2850
→Gretsch Effects
また、直接C.G. Connとは関係無いのは思うのですが、イタリア産の謎めいた 'Multivider' なども登場してこのニッチな市場の裾野を広げます。SonextoneのMultividerやこれと '姉妹機的関係' にあるTekson Color Soundなど、この管楽器 'アンプリファイ探求' において非常に興味深い一台であると言えます。また、1970年代後半にM3 emthreeなる会社から登場した極悪オクターバー、Mini Synthyが奇しくも同じイタリア産であり腰のベルトに装着する '管楽器奏者仕様' なのだから謎は深まるばかり。一方、GretschのエフェクターといえばExpanderfuzzやTremofect、イタリアJenのブランドでも販売された'Play Boy' シリーズなどが代表的ですけど、その妙なデザイン含めこちらもイマイチ全貌が掴めないのですヨ。このTone Dividerは1970年代に入って発売されたもので、4つのツマミにClarinetとSaxophoneの入力切り替えやSound On/Off (Effect On/Off)のスイッチ、そしてNatural、English Horn、Oboe、Mute、Bassoon、Bass Clarinet、Saxophone、Cello、Contra Bass、String、Tubaの11音色からなるパラメータはMaestro Woodwindsあたりを参考にしたっぽい感じ。ここにTremolo、Reverb、Jazzというエフェクツをミックス(外部フットスイッチでコントロール可)するという、まあ、同時代の管楽器用エフェクターで定番の仕様となっております。この金属筐体に描かれた木目調のダサい感じがたまりません。しかし、未だにアコースティックとか 'エレアコ' 系のエフェクターって何で木目調や '暖色系' ばかりなんでしょうか?(笑)。
- 1970年代にあなたは電化したサックスで実験されましたよね。あなたのサックスを電化するにあたり用いたプロセスはどのようなものでしょう?。
そして電子音響とジャズマンを '越境' した 'マッド・サイエンティスト' として唯一無二の存在、ギル・メレをご紹介致しましょう。彼のキャリアは1950年代にBlue Noteで 'ウェストコースト' 風バップをやりながら画家や彫刻家としても活動し、1960年代から現代音楽の影響を受けて自作のエレクトロニクスを製作、ジャズという枠を超えて多彩な実験に勤しみました。そのマッドな '発明家' としての姿を示す画像は上から順に 'Elektor' (1960)、'White-Noise Generator' (1964)、'Tome Ⅳ' (1965)、'The Doomsday Machine' (1965)、'Direktor with Bubble Oscillator' (1966)、'Wireless Synth with Plug-In Module' (1968)といった数々の自作楽器であり、特に1967年にVerveからのリーダー作 'Tome Ⅳ' は、まるでEWIのルーツともいうべきソプラノ・サックス状の自作楽器(世界初!の電子サックス)を開陳したものです。ま、一聴した限りではフツーのサックスと大差ないのですが、彼がコツコツとひとり探求してきたエレクトロニクスの可能性が正式に評価されなかったのは皮肉ですね。そんなメレ独自のアプローチは1971年のSF映画 'The Andromeda Strain' のOSTに到達、EMS VCS3や自作のドラムシンセを駆使して難解な初期シンセサイザーにおける金字塔を打ち立てます。ちなみにこの映画は、まさに今の新型コロナウィルスを暗示したような未知のウィルス感染に立ち向かう科学者たちのSF作品でして、その '万博的' レトロ・フューチャーな未来観の映像美と70年代的終末思想を煽るギル・メレの電子音楽が見事にハマりました。このギル・メレやブルーノ・スポエリ、ドン・エリスらがやったこと、また、ジャズとインドへの接近から 'Space Age' 世代がもたらした意識変革について誰か一冊の本で著しませんかね?。
"エディ・ハリスのグループがロサンゼルスの〈シェリーズ・マンホール〉に出ていたとき、彼のグループはジョディ・クリスチャン(ピアノ)、メルヴィン・ジャクソン(ベース)、リチャード・スミス(ドラムス)で構成されていたが、ハリスとベースのジャクソンが電化楽器を使っており、ジャクソンがアルコ奏法で発する宇宙的サウンドをバックにハリスが多彩な効果を発揮してみせた。2音、3音のユニゾン・プレイはもちろんのこと、マウスピースにふれないでキーのみをカチカチと動かしてブラジルの楽器クイーカのようなリズミックなサウンドを出し、ボサノヴァ・リズムをサックスから叩き(?)出すのである。この奏法はエディ・ハリスが 'マエストロ' の練習中に偶然出てきた独奏的なもので、同席した評論家のレナード・フェザーとともにアッと驚いたものである。ハリスはあとで、この打楽器的な奏法がサックス奏者に普及すればサックス・セクションでパーカッション・アンサンブルができるだろうと語っていたが、たとえそれが冗談にしろ、不可能ではないのだ。ともあれ、エディ '電化' ハリスのステージは、これまで驚異とされていたローランド・カークのあの演奏に勝るとも劣らない派手さと、不思議なサウンドに満ちていて人気爆発中。しかもカークが盲目ということもあって見る眼に痛々しさがある反面、ハリスは2管や3管吹奏をプッシュ・ボタンひとつの操作で、あとはヴォリューム調整用のフット・ペダルを踏むだけで楽々とやってのけているわけだ。エレクトリック・サックスの利点は、体力の限界に挑むようなこれまでのハードワークにピリオドを打たせることにもなりそうだ。ハイノートをヒットしなくても、ヴァイタルな演奏ができる。つまり、人体を酷使することからも解放されるのだ。この点は、連日ステージに出る当のミュージシャンたちにとって、大きな利点でもあるだろう。エディ・ハリスは電化サックスの演奏中は、体が楽だといった。これを誤解してはいけないと思う。決してなまけているのではなく、そういう状態になると、その分のエネルギーを楽想にまわせることになり、思考の余裕ができて、プラスになるという。さらに、エレクトリック・サックスを使う場合、もし人が普通のサックス通りに演奏したら、ヒドい結果になるという。楽に、自然に吹かないと、オーバーブロウの状態でさまにならないそうだ。新しい楽器は新しいテクニックを要求としているわけだが、それで体力の消耗が少しでもすめば、まことに結構ではないか。"
→Maestro Ring Modulator RM-1A
→Maestro Ring Modulator RM-1B
"同じ電化楽器でもトランペットの場合は特性面でかなりの相異がある。電化トランペットの使用で話題になったドン・エリスの場合、やはり種々のアンプを使っているが、サックスとちがって片手でできるトランペット演奏では、もうひとつの手でアンプの同時操作が可能になる。読者は、先月号のカラーページに登場したドン・エリスの写真で、彼がトランペット片手にうつむきながらアンプを操作している光景をご覧になっているはずだ。あの場合、ドン・エリスはいったん吹いたフレーズをエコーにしようとしてるのだが、この 'エコー装置' を使うと 'Electric Bath' (CBS)中の 'Open Beauty' にきかれる不思議な音楽が誕生する。装置の中にはテープ・レコーダーが内蔵されており、いったん吹かれた音がいつまでもエコーとなって反復される仕組みになっている。ドン・エリスは、この手法を駆使し谷間でトランペットを吹くような効果を出しているが、彼はまた意識的にノイズを挿入する。これも片手で吹きながら、もう一方の手でレバーを動かしてガリガリッとやるのである。こうした彼のアイデアは、一種のハプニングとみなしていいし、彼が以前、'New Ideas' (New Jazz)で試みた実験と相通じるものだ。"
"そこにあったのはイノヴェックス社の機器だった。「連中が送ってきたんだ」。マイルスはそう言いながら電源を入れ、トランペットを手にした。「ちょっと聴いてくれ」。機器にはフットペダルがつながっていて、マイルスは吹きながら足で操作する。出てきた音は、カップの前で手を動かしているのと(この場合、ハーモンミュートと)たいして変わらない。マイルスはこのサウンドが気に入っている様子だ。これまでワウワウを使ったことはなかった。これを使うとベンドもわずかにかけられるらしい。音量を上げてスピーカー・システムのパワーを見せつけると、それから彼はホーンを置いた。機器の前面についているいろんなつまみを眺めながら、他のエフェクトは使わないのか彼に訊いてみた。「まさか」と軽蔑したように肩をいからせる。自分だけのオリジナル・サウンドを確立しているミュージシャンなら誰でも、それを変にしたいとは思っていない。マイルスはエフェクト・ペダルとアンプは好きだが、そこまでなのだ。"
Q - わたしはShurre CA20Bというトランペットのマウスピースに取り付けるピックアップを見つけました。それについて教えてください。
A - CA20Bは1968年から70年までShureにより製造されました。CA20BはSPL/1パスカル、-73dbから94dbの出力レベルを持つセラミックトランスデューサーの圧電素子です。それはHammond Organ社のInnovex部門でのみ販売されていました。CA20BはShureのディーラーでは売られておりませんでした。
CA20Bは(トランペット、クラリネットまたはサクソフォンのような)管楽器のマウスピースに取り付けます。穴はマウスピースの横に開けられて、真鍮のアダプターと共にゴムOリングで埋め込みます。CA20Bはこのアダプターとスクリューネジで繋がっており、CA20Bからアンバランスによるハイ・インピーダンスの出力を60'ケーブルと1/8フォンプラグにより、InnovexのCondor RSMウィンド・インストゥルメンツ・シンセサイザーに接続されます。Condor RSMは、管楽器の入力をトリガーとして多様なエフェクツを生み出すHammond Organ社の電子機器です。Condorのセッティングの一例として、Bass Sax、Fuzz、Cello、Oboe、Tremolo、Vibrato、Bassoonなどの音色をアコースティックな楽器で用いるプレイヤーは得ることができます。またCA20Bは、マウスピースの横に取り付けられている真鍮製アダプターを取り外して交換することができます。
Condorはセールス的に失敗し、ShureはいくつかのCA20Bを生産したのみで終わりました。しかし、いく人かのプレイヤーたちがCA20Bを管楽器用のピックアップとしてギターアンプに繋いで使用しました。その他のモデルのナンバーと関連した他の型番はCA20、CA20A、RD7458及び98A132Bがあります。
R - ここには特別話すほどのものはないけどね(笑)。
− マイク・スターンのエフェクターとほとんど同じですね。
R - うん、そうだ(笑)。コーラスとディレイとオクターバーはみんなよく使っているからね。ディストーションはトランペットにはちょっと・・(笑)。でも、Bossのギター用エフェクツはトランペットでもいけるよ。トランペットに付けたマイクでもよく通る。
− プリアンプは使っていますか?。
R - ラックのイコライザーをプリアンプ的に使っている。ラックのエフェクトに関してはそんなに説明もいらないと思うけど、MIDIディヴァイスが入っていて、ノイズゲートでトリガーをハードにしている。それからDigitechのハーモナイザーとミキサー(Roland M-120)がラックに入っている。
− ステレオで出力していますね?。
R - ぼくはどうなってるのか知らないんだ、エンジニアがセッティングしてくれたから。出力はステレオになってるみたいだけど、どうつながっているのかな?。いつもワイヤレスのマイクを使うけど、東京のこの場所だと無線を拾ってしまうから使っていない(笑)。生音とエフェクト音を半々で混ぜて出しているはずだよ。
− このセッティングはいつからですか?。
R - このバンドを始めた時からだ。ハーモナイザーは3、4年使っている。すごく良いけど値段が高い(笑)。トラック(追従性のこと)も良いし、スケールをダイアトニックにフォローして2声とか3声で使える。そんなに実用的でないけど、モーダルな曲だったら大丈夫だ。ぼくの曲はコードがよく変わるから問題がある(笑)。まあ、オクターヴで使うことが多いね。ハーマン・ミュートの音にオクターヴ上を重ねるとナイス・サウンドだ。このバンドだとトランペットが埋もれてしまうこともあるのでそんな時はエッジを付けるのに役立つ。
− E-mu Proteus(シンセサイザー)のどんな音を使っていますか?。
R - スペイシーなサウンドをいろいろ使っている。時間があればOberheim Matrix 1000のサウンドを試してみたい。とにかく時間を取られるからね、この手の作業は(笑)。家にはAkaiのサンプラーとかいろいろあるけど、それをいじる時間が欲しいよ。
− アンプはRolandのJazz Chorus(JC-120)ですね。
R - 2台をステレオで使っている。
この時のランディの足下には、Boss Octave OC-2→T-Wah TW-1→Digital Delay DD-3→Digital Delay/Sampler DSD-3→Super Chorus CH-1をループ・セレクターのPSM-5でまとめております。生音とエフェクト音を半々で混ぜたセッティングから、マウスピースは穴を開けてBarcus-berryの1374が接合されており、8UのラックにはRolandのミキサーM-120、Alesis Quadlaverb、E-mu Proteus、Drawmer DS-201ノイズゲートのほか、Digitechとメーカー不詳のPitchriderなるハーモナイザーが入っておりました。2台のRoland JC-120アンプのセッティングは、想像ですけどPAからラインでJCの 'Return' に入力してプリアンプをバイパス、パワーアンプのスピーカーのみ使用して鳴らしていると思われます。
ちなみに、このBarcus-berryのエレクトレット・コンデンサー・ピックアップ6001の構造をベースにオリジナルで 'マウスピース・ピックアップ' を製作してしまった近藤等則さん。残念ながら一昨年冥界へと旅立たれてしまいましたが(涙)、1979年にニューヨークで必要に迫られて購入したBarcus-berryピックアップから25年ほど経ち、新たにDPAの無指向性ミニチュア・マイクロフォンを流用してオリジナルのピックアップを製作致します。スクリューネジによるピックアップ本体の着脱、ポリプロピレンのスクリーンによる水滴と息の風を防ぐ構造などはBarcus-berry 6001をほぼ踏襲しており、これでベル側のマイクに頼らず 'マウスピース・ピックアップ' ひとつだけで広い帯域を収音します。2007年にその苦労の顛末をこう述べておりました。個人的に最後の 'ひと言' が実に心に沁み入りますヨ(涙)。人生、飽きることなく足掻いてるっていうのが面白いんだよなあ。
"今年を振り返ってみると、いくつかよかったことの一つが、トランペットのマウスピースの中に埋めるマイクをオリジナルに作ったんだ。それが良かったな。ずっとバーカスベリー ってメーカーのヤツを使ってたんだけど、それはもう何年も前から製造中止になってて、二つ持ってるからまだまだ大丈夫だと思ってたんだけど、今年の4月頃だったかな、ふと「ヤベえな」と、この二つとも壊れたらどうするんだ、と思って。なおかつ、バーカスベリー のをずっと使ってても、なんか気に入らないんだよ。自分で多少の改良は加えてたんだけど、それでも、これ以上いくらオレががんばっても電気トランペットの音質は変えられないな、と。ピックアップのマイクを変えるしかない、と。それで、まずエンジニアのエンドウ君に電話して、「エンちゃん、最近、コンデンサーマイクで、小さくて高性能なヤツ出てない?」って訊いたら、「コンドーさん、最近いいの出てますよ。デンマークのDPAってメーカーが、直径5.5ミリのコンデンサーマイクを作っていて、すごくいいですよ」って言うんで、すぐそれをゲットして。
それをマウスピースに埋めるにしても、水を防ぐことと、息の風を防ぐ仕掛けが要るわけだ。今度は、新大久保にあるグローバルって楽器屋の金管楽器の技術者のウエダ君に連絡して、「このソケットを旋盤で作ってくれないかな」ってお願いして、旋盤で何種類も削らして。4ヶ月ぐらいかけてね。で、ソケットができても、今言ったように防水と風防として、何か幕を張ってシールドしないといけないわけだ。それをプラスチックでやるのか、セロファンでやるのか、ポリプロピレンでやるのか。自分で接着剤と6ミリのポンチ買ってきて、ここ(スタジオ)で切って、接着剤で貼り付けて、プーッと吹いてみて、「ダメだ」また貼り付けて、また「良くねーなぁ」って延々やってね(笑)。で、ポリプロピレンのあるヤツが一番良かったんだ。そうすると今度は、ポリプロピレンを接着できる接着剤って少ないんだよ。だから東急ハンズに行って、2種類買ってきたら一つは役に立たなくて、もう一つの方がなんとかくっつきが良くてね。その新しいピックアップのチューニングが良くなってきたのは、ごく最近なんだけどね。音質もだいぶ変わってきた。音質が変わると、自分も吹きやすくなるからね。それが、今年はすごくよかったな。
電気機材も、1Uっていうフォーマットで、あれは第一次世界大戦の頃にできた工業規格のはずなんだよ。第二次世界大戦前の、そのままの規格なんだ。だから、大きいんだよな、重いし。これからやるためには、さらに軽量化・小型化したい。今は5Uで使ってたんだけど、3Uぐらいにはできそうなんだ。最近も、なんていうメーカーだったかな。小さくていいディレイが出てね。1U分のディレイ外して、それに換えてみたり。あがきはいつまでも続くね(笑)。"
②マウスピース(または管体)への加工
③煩雑なセッティング
①は、いわゆるピエゾ・トランスデューサーの持つ根本的な問題です。反応が早く、芯のある中域を捉える反面、低域はもちろん高音域が乏しく、硬くシャリシャリとした音質は '生音' へのこだわりを示す奏者にとって、決して満足のいくものではありません。ある程度プリアンプやEQで補正出来るものの、基本的にはスタンドマイクを立てて、ベルからの生音とピックアップの音色をPAのミキサーで混ぜて出力するのが昔からの方法です。その代わりマウスピース・ピックアップは構造上、ある程度のハウリングには効果を示し、エフェクターの効きが良いです。また、現在のグーズネック式マイクがラインからPAで出力されるのに対してマウスピース・ピックアップは、アンプで再生したものをマイクを立てて収音するのが一般的でした。
②は、マウスピース(管体)にドリルで穴を開け、ハンダでピックアップを接合するという方法に、貴重なマウスピースへの加工を嫌がる奏者が一定以上いたということです。また、一度取り付けてしまうとマウスピースのサイズを変更できないのもマイナス。ピエゾは、取り付け位置によってもサウンドが激変してしまうことから、マウスピースの他にサックスのネック部分、トランペットのリードパイプ部分、ベルの横側に穴を開けて取り付けるなど、いろいろな方法が取られました。まだお手軽なグーズネック式マイクの無かった頃の煩雑さは、そのまま1970年代のフュージョン・ブーム過ぎ去りし後、管楽器のリペア工房で穴の空いた楽器が再びハンダで埋められるべく列を成していたという話からも伺えます。
③は、このマウスピース・ピックアップが、そもそもは 'アンプリファイ' によりエフェクターを積極的に用いる為のアイテムだということです。これは①でも触れましたが、ベル側の '生音' とのミックスでPAに出力する為に、管楽器に対して2回線がステージ上からPAへと引き回されるわけです。PAとしては極力トラブルにならぬように煩雑なセッティングは避けたいのが本音です。そしてもうひとつ補足すれば、現在はコンサートの現場におけるPAシステム全体の再生クオリティが向上したことも大きいでしょうね。
→Viga Music Tools intraMic by HornFx
→Nalbantov Electronics
→Nalbantov Electronics on eBay
→Piezo Barrel Wind Instrument Pickups
→Piezo Barrel Instructions
→vimeo.com/160406148
"The P9 is different internally and has alot of upper harmonics. The P6 (which was the old PiezoBarrel 'Brass') was based on the same design as the 'Wood' but with more upper harmonics and a lower resonant frequency so they do not sound the same."
なるほど〜。実際、以前の 'P6' と比較して高音域がバランス良く出ているなあと感じていたのですが、かなり金管楽器用としてチューニングしてきたことが分かります。一方で以前の 'P6' は木管楽器用との差異は無いとのこと。基本的にはピックアップ本体、ソケット加工済みのマウスピース、ケーブル、ピックアップ内蔵のゲイン調整の為のミニ・ドライバー、複数のソケットが同梱されて販売されております。Bachタイプのマウスピース・サイズは7C、5C、3C、1Cの4種がありますが、このPiezoBarrel 5Cの新旧比較画像からもお判りのように、'P9' 以降は通常タイプのほかショートシャンクのギャップを持った '無印' と 'Faxx製' のBachタイプも用意。そして以前の製品では、真っ直ぐに切削されたアダプターをマウスピースのシャンクを平らに削り取る手間を経て接合しておりましたが、この波形に加工されたアダプターをハンダで接合した方がその強度面でも圧倒的に有利です。ちなみに以前は不定期でMonetteタイプのものもラインナップしておりましたがスティーヴさん曰く、あの分厚い真鍮の切削加工が大変で止めてしまったとのこと(苦笑)。いやホント、金属の穴開け加工って地味に手間かかるんですヨ。
"First, the brass fitting should be heated with a soldering iron and the bottom surface 'tinned' with solder prior to attaching to the mouthpiece.
The Type E fittings provided are designed to fit around the stem of the trumpet mouthpiece to provide a good solder connection. Note that the fitting placement will depend on how far the stem of the mouthpiece fits into the lead pipe or receiver and the shape of the mouthpiece. It is advised to mark the desired position of the brass attachment with mouthpiece attached to the instrument to ensure the attachment will not prevent the mouthpiece from fitting the instrument correctly.
To attach the brass fitting to the mouthpiece you need to secure the mouthpiece so you can work on it without it moving. The mouthpiece will also need to be heated to approximately 300 degrees C depending on the solder, so it will need to be clamped in some material that can withstand this heat.
The mouthpiece needs to be heated until hot enough to melt the solder. Solder should be applied to a small area where the fitting will be attached. Once the solder has formed a smooth blob on the area and has adhered to the mouthpiece stem, you can carefully (and quickly) wipe the solder off with a clean damp cotton cloth. A little more solder should be carefully applied to wet the area and the fitting placed on the mouthpiece stem and kept hot until a good solder joint has been formed. Heat can them be withdrawn and the fitting and mouthpiece allowed to cool. Using a flux (either rosin or acid) during soldering is required to remove oxides and to get a smooth strong joint. The joint should be washed after cooling to remove any flux that may cause corrosion.
The last step is to drill a 2mm or 2.5mm hole into the mouthpiece to allow the sound from the instrument into the pickup. PiezoBarrel pickups work by sound pressure produced by the standing wave inside the instrument - not like a contact mic."
→NeotenicSound AcoFlavor - Acoustic Pick-Up Signal Conditioner ②
→NeotenicSound AcoFlavor: Column
さて、このピエゾによる 'マウスピース・ピックアップ' 使用にあたって必須の唯一無二なアイテム、NeotenicSound AcoFlavor。ホント、こういうエフェクターって今まで無かったんじゃないでしょうか。というか、いわゆる ' エレアコ' のピックアップの持つクセ、機器間の 'インピーダンス・マッチング' がもたらす不均衡感に悩まされてきた者にとって、まさに喉から手が出るほど欲しかった機材がコレなんですヨ。そもそも本機は '1ノブ' のPiezoFitというプロトタイプからスタートしており、それをさらにLimitとFitの '2ノブ' で感度調整の機能を強化した製品版AcoFlavorへと仕上げ始めたのが2017年の暮れのこと。そのいくつかの意見を反映すべく微力ながらお手伝いをさせてもらったのですが、多分、多くの 'エレアコ楽器' のピックアップ自体が持つ仕様の違いからこちらは良いけどあちらはイマイチという感じで、細かな微調整を工房とやり取りしながら煮詰めて行きました。当初、送られてきたのはMaster、Fit共に10時以降回すと歪んでしまって(わたしの環境では)使えませんでした。何回かのやり取りの後、ようやく満足できるカタチに仕上がったのが今の製品版で、現在はLimit 9時、Master 1時、Fit 11時のセッティングにしてちょうど良いですね。ちなみに本機はプリアンプではなく、奏者が演奏時に感じるレスポンスの '暴れ' をピックアップのクセ含めて補正してくれるもの、と思って頂けると分かりやすいと思います。その出音以上に奏者が演奏から体感するフィードバックの点で本機の 'あると無し' じゃ大きく違い、管楽器でPiezoBarrelなどのマウスピース・ピックアップ使用の方は絶対に試して頂きたい逸品です。そう言えば以前、PiezoBarrel主宰のスティーヴさんに下手な英語で本機の 'プレゼン' 含めオススメしたのだけどプリアンプと勘違いしたのか、このピックアップはSSLコンソール(スタジオにあるでっかいミキサー)のEQやヘッドアンプを参考にした内蔵のGainツマミ調整だけでもそのまま使えるよ、ただAcoFlavorのデザインは良いね!という '評価' をもらってしまった(苦笑)。やはり言葉だけでは伝わらない・・。これは使ってみて初めてその '威力' が体感出来るものだと思うのですヨ。ちなみにPiezoBarrelピックアップにはミニ・ドライバーで調整するGainツマミがあるのですが、このAcoFlavor使用の場合はそのGainをフルにして本機のMasterでピックアップの調整を行います。
→Sennheiser Microphone
さて、こちらはサックスによるマイク4種類の比較動画。ここではコンデンサー・マイクのSD Systems LCM 8gとダイナミック・マイクのLDM 94、Beyerdynamicのダイナミック・マイクTG i52が選ばれております。やはりスタンド・マイクに比べるとグーズネック式のものは音質的に相当スポイルされているというか、ライヴという環境での利便性にシフトして設計されている感じがしますね。サックス用で用意されたSD Systems LDM 94は通常のクリップ式のほか、その独特な '3点支持' マウントで 'コンプ感' のある力強い出音により人気を博しております。さて、わたしがラッパに用いているのはSennheiserのe608。スーパーカーディオイドの指向性で、ShureのHPの説明によれば「カーディオイドよりもピックアップ角度が狭く、横からの音を遮断、ただしマイクの背面にある音源に対し少し感度が高くなる」と記しています。環境ノイズや近くの楽器などからの遮音性がより高いため、フィードバックが発生しにくくなるが、使用者は「マイクの正面の位置をモニターに対して意識する必要がある」とのこと。確かにマイクを触ると後方もゴソゴソと感度は高いのが分かります。一方のBeyerdynamic TG i52の指向性はハイパーカーディオイドで、同じくShureのHPの説明によれば「ハイパーカーディオイドには双方向性マイクロフォンの性質がいくらか備わっており、背面に対する感度は高くなっている。しかし、側面からの音の遮断に非常に優れフィードバックに特に強く、スーパーカーディオイドと同じく周囲の音が被りにくい性質。ただし指向性がとても強いため、音源に対するマイクの配置は正確さが求められる」とあります。どちらもよく似た指向性ながらTG i52の方がよりピンポイントで音を狙う設計というわけか。周波数特性としてはe608が40〜16000Hz、TG i52の方は40〜12000Hzとのことで、この辺も指向性の違いに反映されているのでしょう。ダイナミック・マイクはコンデンサー・マイクに比べて特に高域の周波数レンジが狭く、近接のオンマイクにセッティングしてマイク・プリアンプで適正なゲインを持ち上げてやらないと機能を発揮しません(ファンタム電源を誤ってOnにするのは厳禁です!)。
R - 今回のバンドのようにギターの音が大きい場合には、エフェクトを使うことで私の音が観客に聴こえるようになるんだ。大音量の他の楽器が鳴る中でもトランペットの音を目立たせる比較的楽な方法と言えるね。トランペットとギターの音域は似ているので、エフェクターを使い始める以前のライヴでは常にトラブルを抱えていた。特に音の大きいバンドでの演奏の場合にね。それがエフェクターを使い始めた一番の理由でもあるんだよ。ピッチ・シフターで1オクターヴ上を重ねるのが好きだね。そうするとギターサウンドにも負けない音になるんだ。もし音が正しく聴こえていれば、アコースティックな音ともマッチしているはずだしね。
- ライヴではその音を聴いていて、エッジが増すような感じがしました。
R - うん、だからしっかりと聴こえるんだ。それに他の楽器には全部エレクトリックな何かが使われているから、自分もエレクトリックな状況の一部になっているのがいい感じだね。
- そのピッチ・シフトにはBossのギター用マルチ・エフェクター、ME-70を使っていましたね?。
R - うん、そうだ。ディレイなどにもME-70を使っている。ただ使うエフェクターの数は少なくしているんだ。というのもエフェクターの数が多すぎるとハウリングの可能性も増えるからね。ME-70は小型なのも気に入っている。大きな機材を持ち運ぶのは大変だし、たくさんケーブルを繋ぐ必要もないからね。
- そのほかのエフェクターは?。
R - BossのオートワウAW-3とイコライザーのGE-7、ほかにはErnie Ballのヴォリューム・ペダルだよ。本当はもっとエフェクツを増やしたい気持ちもあるんだけど、飛行機で移動するときに重量オーバーしてしまうから無理なのさ。もっとエフェクトが欲しいときにはラップトップ・コンピュータに入っているデジタル・エフェクツを使うようにしているね。
- マイクはどんなものを?。
R - デンマークのメーカーDPA製の4099というコンデンサー・マイクだ。このマイクだと高域を出すときが特に楽なんだ。ファンタム電源はPA卓から送ってもらっている。
- 昔はコンタクト・ピックアップを使っていましたよね?。
R - うん、エフェクツを使い始めた頃はBarcus-berryのピックアップを使っていたし、マウスピースに穴を開けて取り付けていた。ラッキーなことに今ではそんなことをしなくてもいい。ただ、あのやり方もかなり調子良かったから、悪い方法ではなかったと思うよ。
- ちなみにお使いのトランペットは?。
R - メインはYamahaのXeno YTR-8335だ。マウスピースは・・いつも違うものを試しているけど、基本的にはBach 2 1/2Cメガトーンだね。
- 弟のマイケルさんとあなたは、ホーンでエフェクツを使い始めた先駆者として知られていますが、なぜ使い出したのでしょうか?。
R - それは必要に迫られてのことだった。つまり大音量でプレイするバンドでホーンの音を際立たせることが困難だったというのが一番の理由なんだ。最初は自分たちの音が自分たち自身にちゃんと聴こえるようにするのが目的だったんだよ。みんなが私たちを先駆者と呼ぶけど、実際はそうせざるを得ない状況から生まれたのさ。
- あなたがエフェクターを使い始めた当時の印象的なエピソードなどはありますか?。
R - 1970年当時、私たちはDreamsというバンドをやっていた。一緒にやっていたジョン・アバークロンビーはジャズ・プレイヤーなんだけど、常にワウペダルを持って来ていたんだよ。彼はワウペダルを使うともっとロックな音になると思っていたらしい。ある日、リハーサルをやっていたときにジョンは来られなかったけど、彼のワウペダルだけは床に置いてあった。そこで私は使っていたコンタクト・ピックアップをワウペダルにつなげてみたら、本当に良い音だったんだ。それがワウを使い始めたきっかけだよ。それで私が "トランペットとワウって相性が良いんだよ" とマイケルに教えたら、彼もいろいろなエフェクターを使い始めたというわけだ。それからしばらくして、私たちのライヴを見に来たマイルス・デイビスまでもがエフェクターを使い出してしまった、みんなワウ・クレイジーさ(笑)。
- マイケルさんとは "こっちのエフェクターが面白いぞ" と情報交換をしていたのですか?。
R - うん、よくやっていたよ。彼の方が私よりもエフェクツにハマっていたから、時には彼がやっていることを理解できないこともあったもの。でも私たちはよく音楽に関する情報を交換していたね。特に作曲に関してや、バンドの全体的なサウンドに関していつも話をしていたよ。それにお互いに異なるエフェクツを試すことも多かった。サックスに合うエフェクトとトランペットに合うエフェクトは若干違うんだよ。ワウは彼のサックスには合わなかったよ(笑)。
"ローインピーダンス仕様のギターのバランス出力を入力端子に接続するときは、このスイッチを押し下げてください。TRS端子による接続が必要なバランス接続では、最高のダイナミックレンジと低ノイスの環境が得られます。"
● for amplifying woodwinds and brass
● exciting and dramatic
● new tonal dimensions
More than mere amplification. A convenient transistorized package complete with microphone attachments for saxes. clarinets and brass. Will provide variety of sounds. singly and in unison, octaves up and down, mellow of bright.
しかし 'Inquire for details and prices' と強調されているのを見ると日本から現物が届いておらず、カタログでアナウンスされたものの米国では発売されなかった感じですね。
Ace Toneが鍵盤奏者やギター奏者のみならず、管楽器の 'アンプリファイ' にもアプローチしていたことはほとんど知られておりません。そんなAce Tone随一の謎に迫るべく、'スイングジャーナル' 誌1969年3月号に掲載された座談会「来るか電化楽器時代! - ジャズとオーディオの新しい接点 -」から掲載します。こちらは4名の識者、'スイングジャーナル ' 誌編集長の児山紀芳氏、テナーサックス奏者の松本英彦氏、オーディオ評論家の菅野沖彦氏、そして当時Ace Toneことエース電子工業専務であった梯郁太郎氏らが 'ジャズと電気楽器の黎明期' な風景について興味深く語り合います。ここでの議論の中心として、やはり三枝文夫氏と同じく梯郁太郎氏もこの '新たな楽器' に対してなかなか従来の奏者やリスナーが持つ価値観、固定観念を超えて訴えるところまで行かないことにもどかしさがあったのでしょうね。しかし、この頃からすでに現在のRoland V-DrumsやAerophoneの原初的アイデアをいろいろ探求していたとは・・梯さん凄い!。また、管楽器とピエゾ・ピックアップの過剰なレスポンスに関する 'エレアコ' の含蓄ある話が聞けることも貴重です。
- 児山
今回の座談会は、去年あたりから市販されて非常に話題になっているエレクトリック・インストゥルメントとしてのサックスやドラムといったようなものが開発されていますが、その電気楽器の原理が一体どうなっているのか、どういう特性をもっているのか、そしてこういったものが近い将来どうなっていくだろうかといったようなことを中心にお話を聞かせていただきたいと思います。そこでまずエース電子の梯さんにメーカーの立場から登場していただき、それからテナー奏者の松本英彦さんには、現在すでにエレクトリック・サックスを時おり演奏していらっしゃるという立場から、菅野沖彦さんには、ジャズを録音していくといった、それぞれの立場から見たいろんなご意見をお伺いしたいと思うんです。
まず日本で最初にこの種の製品を開発市販された梯さんに電化楽器というものの輪郭的なものをお話願いたいと思うんですが。
- 梯
電気的に増幅をして管楽器の音をとらえようというのは、もう相当以前からあったんですが、実際にセルマーとかコーンとかいった管楽器の専門メーカーが商品として試作したのは3年ぐらい前です。それが2年ぐらい前から市販されるようになったわけです。
- 児山
これは結局いままでのエレクトリック・ギターなどとは別であると考えていいわけですか。
- 梯
ええ、全然別なんです。これらの電化管楽器が、ギターなどと一番違うところは、コードのない単音楽器だけができる電気的な冒険というのが一番やりやすいわけです。といいますのは、コードになった時点からの増幅段というのは絶対に忠実でなければならない。ところが単音というのはどんな細工もできるわけです。この単音のままですと、これはまだ電子音なんです。そこに人間のフィーリングが入って初めて楽音になりますが、そういった電気的な波形の冒険というのが、単音楽器の場合いろいろなことができるわけです。その一例として、オクターブ上げたり下げたりということが装置を使うと簡単に実現することができるんです。コードの場合はその一音づつをバラバラにしてオクターブ上げたり下げたりしてまた合接する・・これはちょっと不可能なわけですね。
- 児山
これら電化楽器のメリットというか特性的なことをいまお話し願いましたが、そこでいかにして電気的な音を出しているのかという原理をサックスに例をとってわかりやすくお願いしたいんですが。
- 梯
現在市販されているものを見ますと、まずマイクロフォンを、ネックかマウスピースか朝顔などにとりつける。そのマイクもみんなエア・カップリング・マイク(普通のマイク)とコンタクト・マイク(ギターなどについているマイク)との中間をいくようなそういったマイクです。ですからナマのサックスの音がそのまま拾われてるんじゃなくて、要するに忠実度の高いマイクでスタジオでとらえた音とはまったく違うものなんですよ。むしろ音階をとらえてるような種類のマイクなんです。音色は、そのつかまえた電気のスペースを周波数としてとらえるわけです。それを今度はきれいに波を整えてしまうわけです。サックスの音というのは非常に倍音が多いものですから基本波だけを取り出す回路に入れて今度はそれを1/2とか1/4とか、これは卓上の計算機のほんの一部分に使われている回路ですけど、こういったものを使ってオクターブ違う音をつくったりするわけですよ。これらにも2つのモデルがあって、管楽器にアタッチメントされている物ですと、むしろ奏者が直ちに操作できることを主眼に置いて、コントロール部分を少なくして即時性を求めてるものと、それから複雑な種々の操作ができるということに目標を置いた、据え置き型(ギブソンのサウンド・システム)といったものがあるわけです。
- 児山
これで大体原理的なことはわかりますが。
- 菅野
わかりますね。
- 松本
ところが、これから先がたいへんなんだ(笑)。
- 児山
じゃ、そのたいへんなところを聞かせてください。それに現在松本さんはどんな製品を・・。
- 松本
現在セルマーのヴァリトーンです。しかし、これどうも気に入らないので半年かかっていろいろ改造してみたんだけど、まだまだ・・。サックスは、サックスならではの音色があるんですよ。それがネックの中を通して出る音はまず音色が変わるんですね。それから、音が出てなくてもリードなどが振動していたり、息の音などが拾われて、オクターブ下がバァーッと出るんですよ。
- 梯
それはコンタクト・マイクの特性が出てくるわけなんです。
- 菅野
わずかでもエネルギーがあればこれは音になるわけですね。
- 梯
ですから、マウス・ピースに近いところにマイクをつけるほど、いま松本さんのいわれたような現象が起るわけなんです。かといって朝顔につけるとハウリングの問題などがあるわけなんです。
- 松本
ちっちゃく吹いても、大きなボリュームの音が出るというのは、サックスが持つ表情とか感情というものを何か変えてしまうような気がするねェ。一本調子というのかなあ。それに電気サックスを吹いていると少し吹いても大きな音になるから、変なクセがつくんじゃないかなんて・・。初めオクターブ下を使ってたとき、これはゴキゲンだと思ったけど、何回かやってると飽きちゃうんだね。しかし、やっぱりロックなんかやるとすごいですよ。だれにも音はまけないし、すごい鋭い音がするしね。ただ、ちょっと自分自身が気に入らないだけで、自分のために吹いているとイージーになって力いっぱい吹かないから、なまってしまうような・・。口先だけで吹くようになるからね。
- 児山
それもいいんじゃないですか。
- 松本
いいと思う人もありますね。ただぼくがそう思うだけでね。電気としてはとにかくゴキゲンですよ。
- 児山
いま松本さんが力強く吹かなくても、それが十分なボリュームで強くでるということなんですが、現在エレクトリック・サックスの第一人者といわれるエディ・ハリスに会っていろんな話を聞いたときに、エレクトリック・サックスを吹くときにはいままでのサックスを吹くときとはまったく別のテクニックが必要であるといってました。
- 松本
そうなんですよ。だからそのクセがついてナマのときに今度は困っちゃうわけ。
- 児山
だから、ナマの楽器を吹いているつもりでやると、もうメチャクチャになって特性をこわしてしまうというわけです。結局エレクトリック・サックスにはそれなりの特性があるわけで、ナマと同じことをやるならば必要ないわけですよ。その別のものができるというメリット、そのメリットに対して、まあ新しいものだけにいろんな批判が出てると思うんですよね。いま松本さんが指摘されたように音楽の表情というものが非常に無味乾燥な状態で1本やりになるということですね。
- 松本
ただこの電気サックスだけを吹いていれば、またそれなりの味が出てくるんだろうと思うんですが、長い間ナマのサックスの音を出していたんですからね・・。これに慣れないとね。
- 児山
やっぱりそういったことがメーカーの方にとっても考えていかなきゃならないことなんですかね。
- 梯
ええ。やはり電子楽器というのは、人間のフィーリングの導入できるパートが少ないということがプレイヤーの方から一番いやがられていたわけです。それがひとつずつ改良されて、いま電子楽器が一般に受け入れられるようになった。しかし、このエレクトリック・サックスというのはまだ新しいだけに、そういう感情移入の場所が少ないんですよ。
- 松本
ぼくが思うのは、リードで音を出さないようなサックスにした方がおもしろいと思うな。だって、実際に吹いている音が出てくるから、不自然になるわけですよ。
- 梯
いま松本さんがいわれたようなものも出てきてるわけなんですよ。これは2年前にフランクフルトで初めて出品された電気ピアニカなんですが・・。
- 松本
吹かなくてもいいわけ・・。
- 梯
いや吹くんです。吹くのはフィーリングをつけるためなんです。これは後でわかったのですが、その吹く先に風船がついていて、その吹き方の強弱による風船のふくらみを弁によってボリュームの大小におきかえるという方法なんです。ですから人間のフィーリングどうりにボリュームがコントロールされる。そして鍵盤の方はリードではなく電気の接点なんです。ですからいままでのテクニックが使えて、中身はまったく別のものというものも徐々にできつつあるわけなんです。
- 松本
電気サックスの場合、増幅器の特性をなるべく生かした方が・・いいみたいね。サックスの音はサックスの音として、それだけが増幅されるという・・。
- 菅野
いまのお話から、われわれ録音の方の話に結びつけますと、電子楽器というものは、われわれの録音再生というものと縁があって近いようで、その実、方向はまったく逆なんですよね。電子楽器というのは新しい考え方で、新しい音をクリエートするという方向ですが、録音再生というのは非常に保守的な世界でして、ナマの音をエレクトロニクスや機器の力を使って忠実に出そうという・・。というわけで、われわれの立場からは、ナマの自然な楽器の音を電気くさくなく、電気の力を借りて・・という姿勢(笑)。それといまのお話で非常におもしろく思ったのは、われわれがミキシング・テクニックというものを使っていろいろな音を作るわけですが、電子楽器を録音するというのは、それなりのテクニックがありますが、どちらかというと非常に楽なんです。電子楽器がスタジオなりホールなりでスピーカーからミュージシャンが音を出してくれた場合には、われわれはそれにエフェクトを加える必要は全然ない。ですからある意味ではわれわれのやっていた仕事をミュージシャンがもっていって、プレーをしながらミキシングもやるといった形になりますね。そういうことからもわれわれがナマの音をねらっていた立場からすれば非常に残念なことである・・と思えるんですよ。話は変わりますが、この電化楽器というのは特殊なテクニックは必要としても、いままでの楽器と違うんだと、単にアンプリファイするものじゃないんだということをもっと徹底させる必要があるんじゃないですか。
- 梯
現在うちの製品はマルチボックスというものなんですが、正直な話、採算は全然合ってないんです。しかし、電子楽器をやっているメーカーが何社かありますが、管楽器関係のものが日本にひとつもないというのは寂しいし、ひとつの可能性を見つけていくためにやってるんです。しかし、これは採算が合うようになってからじゃ全然おそいわけですよ。それにつくり出さないことには、ミュージシャンの方からご意見も聞けないわけですね。実際、電子管楽器というのは、まだこれからなんですよ。ですからミュージシャンの方にどんどん吹いていただいて、望まれる音を教えていただきたいですね。私どもはそれを回路に翻訳することはできますので。
- 菅野
松本さん、サックスのナマの音とまったく違った次元の音が出るということがさきほどのお話にありましたね。それが電子楽器のひとつのポイントでもあると思うんですがそういう音に対して、ミュージシャンとしてまた音楽の素材として、どうですか・・。
- 松本
いいですよ。ナマのサックスとは全然違う音ならね。たとえば、サックスの「ド」の音を吹くとオルガンの「ド」がバッと出てくれるんならばね。
- 菅野
そういう可能性というか、いまの電気サックスはまったく新しい音を出すところまでいってませんか。
- 梯
それはいってるんですよ。こちらからの演奏者に対しての説明不十分なんです。要するに、できました渡しました・・そこで切れてしまってるわけなんです。
- 菅野
ただ、私はこの前スイングジャーナルで、いろんな電化楽器の演奏されているレコードを聴いたんですが、あんまり変わらないのが多いんですね。
- 児山
どういったものを聴かれたんですか?。
- 菅野
エディ・ハリスとか、ナット・アダレーのコルネット、スティーブ・マーカス・・エディ・ハリスのサックスは、やっぱりサックスの音でしたよ。
- 梯
あのレコードを何も説明つけずに聴かせたら、電子管楽器ということはわからないです。
- 児山
そうかもしれませんが、さきほど菅野さんがおっしゃったようにいまそういったメーカーの製品のうたい文句に、このアタッチメントをつけることによってミュージシャンは、いままでレコーディング・スタジオで複雑なテクニックを使わなければ創造できなかったようなことをあなた自身ができる、というのがあるんです。
- 菅野
やはりねェ。レコーデットされたような音をプレイできると・・。
- 梯
これはコマーシャルですからそういうぐあいに書いてあると思うんですが、水準以上のミュージシャンは、そういう使い方はされていないですね。だからエディ・ハリスのレコードは、電気サックスのよさを聴いてくださいといって、デモンストレーション用に使用しても全然効果ないわけです。
- 菅野
児山さんにお聞きしたいんですが、エディ・ハリスのプレイは聴く立場から見て、音色の問題ではなく、表現の全体的な問題として電子の力を借りることによって新しい表現というものになっているかどうかということなんですが・・。
- 児山
そもそもこの電気サックスというのは、フランスのセルマーの技師が、3本のサックスを吹く驚異的なローランド・カークの演奏を見てこれをだれにもできるようにはならないものかと考えたことが、サックスのアタッチメントを開発する動機となったといわれてるんですが、これもひとつのメリットですよね。それに実際にエディ・ハリスの演奏を聴いてみると、表情はありますよ。表情のない無味乾燥なものであれば絶対に受けるはずがないですよ。とにかくエディ・ハリスは電気サックスを吹くことによってスターになったんですからね。それにトランペットのドン・エリスの場合なんか、エコーをかけたりさらにそれをダブらせたりして、一口でいうならばなにか宇宙的なニュアンスの従来のトランペットのイメージではない音が彼の楽器プラス装置からでてくるわけなんです。それに音という意味でいうならば、突然ガリガリというようなノイズが入ってきたり、ソロの終わりにピーッと鋭い音を入れてみたり、さらにさきほど松本さんがいわれたように吹かなくても音がでるということから、キーをカチカチならしてパーカッション的なものをやったりで・・。
- 松本
私もやってみましたよ。サックスをたたくとカーンという音が出る。これにエコーでもかけると、もうそれこそものすごいですよ(笑)。
- 児山
エディ・ハリスの演奏の一例ですが、初め1人ででてきてボサ・ノバのリズムをキーによってたたきだし、今度はメロディを吹きはじめるわけなんです。さらに途中からリズム・セクションが入るとフットペダルですぐにナマに切り換えてソフトな演奏をするというぐあいなんですよ。またコルトレーンのような演奏はナマで吹くし、メロディなんかではかなり力強くオクターブでバーッと・・。つまり、彼は電気サックスの持つメリットというものを非常に深く研究してました。
- 菅野
それが電化楽器としてのひとつのまっとうな方法なんじゃないですか。でも、あのレコードはあんまりそういうこと入ってなかったですよね。
- 児山
つまり、エディ・ハリスのレコードは完全にヒットをねらったものでして、実際のステージとは全然別なんです。また彼の話によると、コルトレーンのようなハード・ブローイングを延々20分も吹くと心臓がイカレちゃうというわけです(笑)。そしてなぜ電気サックスを使いだしたかというと、現在あまりにも個性的なプレイヤーが多すぎるために、何か自分独自のものをつくっていくには、演奏なり音なりを研究し工夫しなければならない。たとえば、オーボエのマウス・ピースをサックスにつけたりとかいろんなことをやっていたが、今度開発された電気サックスは、そのようないろいろなことができるので、いままでやってたことを全部やめてこれに飛び込んだというんですよ。
- 菅野
非常によくわかりますね。
- 児山
ラディックというドラム・メーカーが今度電化ヴァイブを開発して、ゲーリー・バートンが使うといってましたが、彼の場合は純粋に音楽的に、そのヴァイブがないと自分のやりたいことができないというわけですよ。なぜかというと、自分のグループのギター奏者が、いままでのギター演奏とは別なフィードバックなどをやると、ほかの楽器奏者もいままで使ってなかったようなことをやりだした。そういう時にヴァイブのみがいままでと同じような状態でやっているというのは音楽的にもアンバランスであるし、グループがエレクトリック・サウンズに向かったときには自分もそうもっていきたいというわけなんですよ。もしそれをヴァイブでやることができれば、どういう方向にもっていけるかという可能性も非常に広いものになるわけですよね。
- 梯
それから、いままでの電子楽器というのは、とにかくきれいな音をつくるということだけから音が選ばれた。ところが音の種類には不協和音もあればノイズもある。そのことをもう一度考えてみると、その中に音の素材になりうるものがたくさんあるわけです。たとえばハウリングですが、以前にバンクーバーのゴーゴー・クラブへいったとき、そこでやってたのがフィードバックなんです。スピーカーのまん前にマイクをもってきてそいつを近づけたり離したりして、そこにフィルターを入れてコントロールして、パイプ・オルガンの鍵盤でずっとハーモニーを押さえ続けてるようなものすごく迫力のある音を出すんです。そんなものを見て、これはどうも電子楽器の常識というものをほんとうに捨てないと新しい音がつくれないと思いましたね。
- 児山
そうですね。ですから、いまこういう電子楽器、あるいは楽器とは別なエレクトリックな装置だけを使って、ジャズだといって演奏しているグループもあるわけです。まあそれにはドラムやいろいろなものも使ったりするわけですが、いわゆる発振器をもとに非常に電気的な演奏をしているわけなんですよ。
- 松本
ただ音は結局電子によってでるんだけど、オルガン弾いてもサックス吹いても同じ音が出るかもしれない。弾いてる人の表情は違うけれども、そういうのがあったらおもしろいと思いますね。
- 菅野
それにもうひとつの問題は、発振器をもとにしたプレーは、接点をうごかしていくといった電子楽器と根本的に違うわけだ。電気サックスなどは、松本さんがいわれているようにナマの音が一緒に出てくるという。そこが問題ですね。だからナマの音も積極的に利用して、ナマの音とつくった音を融合して音楽をつくっていくか、それともナマの音はできるだけ消しちゃって電子の音だけでいくか・・。
- 児山
それはミュージシャン自身の問題になってくるんじゃないかな。たとえばリー・コニッツなどのようにだれが聴いてもわかる音色を持っている人は変えないですね。自分の音を忠実に保ちながらオクターブでやるとか・・。
- 梯
しかしその場合、音色は保ち得ないんです。つまりその人その人のフィーリング以外は保ち得ないんですよ。
- 児山
なるほど、そうすると音楽的な内容がその個性どうりにでてくるということなんですね。
- 菅野
一般に音というものはそういうものの総合なんで、物理的な要素だけを取り上げるのは困難なわけです。そういったすべてのものがコンバインされたものをわれわれは聴いているわけですから、その中からフィーリングだけを使っても、リー・コニッツ独特なものが出てくれば、これはやはりリー・コニッツを聴いてるわけですよ。
- 松本
それならいいけどサックスというのはいい音がするわけですよ。それをなまはんかな拡声装置だといけない。それだとよけいイヤになるんですよ。
- ついに出現した電気ドラム -
- 児山
ニューポートに出演したホレス・シルヴァー・クインテットのドラマー、ビリー・コブハムがハリウッド社のトロニック・ドラムという電気ドラムを使用していましたが、あれはなんですか。
- 梯
うちでも実験をやっています。ロックなどの場合、エレキのアンプが1人に対して200W、リードが200Wならベースは400Wくらい。そうなってくるといままで一番ボリュームがあったドラムが小さくなってきたわけですよ。最初はドラムの音量をあげるだけだったのですが、やってみるとマイクのとりつけ方によって全然ちがった効果が出てきたわけですよ。
- 菅野
それは具体的に各ドラム・セットの各ユニットに取り付けるわけですか。
- 梯
最初は単純に胴の中にマイクを取り付けただけでしたが、いまはコンタクト・マイクとエア・カップリング・マイクの共用でやっていますね。
- 菅野
シンバルなんかは・・。
- 梯
バスドラム、スネア、タム・タムにはついていますが、シンバルはちょっとむずかしいのです・・。でもつけてる人もいるようですね。
- 菅野
ではいまの形としては、新しい音色をつくろうとしているわけですね。
- 梯
そうですね。現在ははっきりと音色変化につかってますね。
- 松本
でもやはりこの電気ドラムとてナマの音が混じって出るわけですよね。ナマの音がでないようにするにはできないのですか。
- 梯
それはできるんですよ。市販はしてないんですが、ドラムの練習台のようなものの下にマイクをセッティングするわけなんですよ。いままでのドラム以外の音も十分でますがシンバルだけはどうもね。らしき音はでるんですが。
- 松本
いままでの何か既成があるからでしょう。
- 梯
そうですね。だからシンバルはこういう音なんだと居直ってしまえばいいわけ・・。それぐらいの心臓がなきゃね(笑)。
- 菅野
本物そっくりのにせものをつくるというのはあまりいいことではない。あまり前向きではないですよ。よくできて本物とおなじ、それなら本物でよりいいものを・・。
- 松本
だから電気サックスでも、ナマの音をだそうとしたんじゃだめですね。これじゃ電気サックスにならない。
- 梯
松本さんにそういわれるとぐっとやりやすくなりますよ(笑)。
- 児山
電気サックスというのはだいたいいくらぐらいなんですか?。
- 松本
ぼくのは定価85万円なんですよ。でもね高いというのは輸入したということですからね。そのことから考えると・・。
- 梯
松本さんの電気サックスはニューオータニで初めて聴いたんです。これは迫力がありましたね。
- 松本
すごい迫力です。でも、それに自分がふりまわされるのがいやだから・・。
- 梯
こちらから見たり聴いたりしていると松本さんが振り回しているように見えるから、それは心配いらないですよ(笑)。
- 松本
それに運ぶのがどうもねェ。いままではサックスひとつ持ってまわればよかった。ギターなんかじゃ最初からアンプを持って歩かなければ商売にならないとあきらめがあるんですが、ぼくはなにもこれがなくたってと考えるから・・。そういうつまらないことのほうが自分に影響力が大きい・・(笑)。
- 児山
やはりコンサートなどで、おおいにやっていただかないと、こういった楽器への認識とか普及とかいった方向に発展していかないと思いますので、そういう意味からも責任重大だと思います。ひとつよろしくお願いします。それに、いまアメリカあたりでは電子楽器が非常に普及してきているわけなんですよ。映画の音楽なんかも、エレクトリック・サウンズ、エレクトリック・インスツルメントで演奏するための作曲法なんていうのはどうなるんですかねェ・・。
- 松本
これがまたたいへんな問題ですが、非常にむずかしいですね。
- 児山
それがいまの作曲家にとって一番頭のいたいことになってるんですね。
- 菅野
あらゆる可能性のあるマルチプルな音を出しうる電化楽器が普及すれば、新しい記号をつくるだけでもたいへんですね。
- 松本
そのエレクトリック・インスツルメントのメーカーだって指定しなければならないし・・。作曲家もその楽器も全部こなさなきゃならないですからね。
- 児山
そのように色々な問題もまだあるわけなんですが、現実にはあらゆる分野の音楽に、そしてもちろんジャズの世界にも着々と普及してきつつあるわけなんです。この意味からも電化楽器の肯定否定といった狭い視野ではなく、もっと広い観点から見守っていきたいですね。
- 梯
あのね、三味線なんですよ。三味線のルーツは中国だけど、日本独特のアイディアが加わったんです。日本の三味線は、一の糸(最も低音の弦、ギターとは数え方が逆)だけが上駒(ギターで言うナットにあたる部分)がなくて指板に触れている。だから、二の糸、三の糸の弦振動は楕円運動で上下左右対称に振動するのに対して、一の糸は非対称の波形で振動して、なおかつ弦が指板に当たることで独特の歪み音を作っていたわけです。それが三味線の演奏上、非常に生きていた。そしてその後、三味線を見習ったわけじゃなく、ギタリストがそういう音を欲しがったんです。耳で見つけ出してね。あとから考えると、昔の人もファズ的な音の必要性を感じたんでしょう。3本の弦のうち1本を犠牲にするほどの意味を持っていたわけですから。
- 1960年代当時は、どうやってあの音を模索したんですか?。
- 梯
プレイヤーの皆さんはいろんなことを試しましたよ。スピーカーのコーン紙を破ってみたりしてね。もちろんどれも結果的には失敗だったんですけど、音としては、弾いたものが非対称に振動して、その時に原音とまったく異なった倍音構成を持つ音をともなって出てくるというのがファズの概念だったんじゃないかな。そもそもファズの定義がありませんでしたし、電気回路として考えたら無着苦茶な回路なんです。でも音楽家の耳がその音を要求したことでそれが生まれた。頭の堅い電気屋にはとうてい出てこない回路ですよ。
- 当時すでにアンプに大入力を入れたオーバードライブ・サウンドは発見されてましたよね?。
- 梯
ありましたよ。ただ、オーバードライブは入力信号が左右対称で、ギターの音っていうのはバーン!と弾いた時が振幅が大きくて、だんだん小さくなっていきますよね。その上下のピークがアンプ側によって削られる、これが技術的に見たオーバードライブの音だった。特にギターは、バーンと弾いた時の振幅が非常に大きいから歪むことが多かったんです。で、当時のアンプはすべて真空管ですよね。真空管はセルフ・バイアスという機能をちゃんと持っていて、大きな信号が入ってくるとバイアス点が変わって歪むポイントも変わるんですよ。そうすると独特の歪みになる。これが、同じ歪みでもトランジスタと比べて真空管の歪みの方が柔らかいとか、耳あたりがいいと感じる理由なんです。まぁ、オーバードライブとかディストーションとか、呼び分けるようになったのはもっとあとの話でね、中でもファズは波形を非対称にするものだから、独立した存在でした。
- マエストロのファズ・トーンが発売された1962年頃、梯さんはすでにエース電子を設立していますが、その当時日本でファズは話題になったんですか?。
- 梯
ほとんど使われなかったですね。ジミ・ヘンドリクスが出てきてからじゃないかな、バーっと広まったのは。GSの人たちはそんなに使ってなかったですよ。使っていたとしても、使い方がまだ手探りの段階だったと思います。
- 国内ではハニーが早くからファズを製作していましたよね。ハニーはトーンベンダー・マークⅠを参考にしたという説もありますが。
- 梯
いやいや、そんなことはないんですよ。彼ら自身が耳で決めたのだと思います。ハニーを設計した人物はその後にエーストーン、ローランドに入社した人ですからその辺の事情は聞いてますけど、ハニーは歪んだ音にエッジをつけて微分する・・要するに低音部を抑えて、真ん中から上の音を強調する回路になっていて、当時としては新しい種類の音でしたね。
- エーストーンも今や名機とされるファズ・マスターFM-2、そしてFM-3を発売しています。これらは70年代に入った頃に発売されていますが、当時の売れ行きはどうでしたか?。
- 梯
両方ともよく売れてましたよ。よくハニーとの関連について聞かれるんだけど、設計者は別の人です。
- そしてその後にローランドを設立するわけですが、ローランド・ブランドではBeeGeeやBeeBaaといったファズを早々に発表しています。やはり需要はあったということですよね?。
- 梯
ありましたね。鍵盤なんかとは違って店頭で売りやすい商品だったのと、その頃にはファズがどういうものかということをお客さんもわかってきていたから。あと面白い話があって、ローランドのアンプ、JC-120の開発もファズと同時期に進めていたんです。根本に戻るとこのふたつは同時発生的に始まっていて、片一方は歪み、片一方はクリーンという対極的な内容のものを作ろうとしていたんですね。そしてJCのコーラスのエンジン部分を抜き出したのが、単体エフェクターのCE-1なわけです。
- そうだったんですね。また、当時の特徴として、ファズとワウを組み合わせたモデルも多かったですよね?。ローランドだとDouble Beat (AD-50)なんかも出てますし。
- 梯
そうですね。ファズを使うことでサスティンが伸びるでしょ。そのサスティンを任意に加工できるのがワウだったんです。音量を変えたり、アタックを抑えてだんだん音が出るようにしたりできたから。
- 当時を改めて振り返って、思うところはありますか?。
- 梯
ハードとソフト、要するにメーカーとプレイヤーの関係は、ハードが進んでいる場合もあるし、ソフトが進んでいる場合もあるんですけど、ファズに関しては音楽家が一歩先を行っていたということですね。それを実現するのに、たまたま半導体が使えたことでこれだけ普及したんだと思います。
- なるほど。その後70年代後半〜90年頃まで 'ファズ' 自体が消える時代がありますが。
- 梯
いや、消えたんじゃなくて、ハード・ロックが出てきて音質がメタリックなものに変わっただけなんです。当初のファズのようにガンガン音をぶつけるんではなく、メロディを弾くためにああいう音に変わった。メタル・ボックスとか、メタライザーとかって名前をつけてましたけど、あれはファズの次の形というか、ファズがあったからこそ見つかった音なわけです。時代で考えてもそうで、ファズがあれだけ出回ったことで、次にハード・ロックが出てきたという自然な流れがあったんだと思います。
- そして90年代にはグランジ/オルタナの流行によって、ファズが再評価されるようになりますね。
- 梯
それは音楽の幅が広がったからですよ。当初、ファズは激しい音楽の部類にしか使われなかったけど、ギターの奏法面でも向上とともに、最初にあった音が見直された。メタリックに歪むものより、あえて昔のファズであったり、OD-1であったりの音でメロディックに弾こうとしたんでしょうね。
- 今ファズを製作している各メーカー、ガレージ・メーカーに対して、梯さんが思うことは?。
- 梯
新しい人が新しい目標でやられるのはいいことです。でも、特定のプレイヤーの意見だけではダメ。10人中10人に受け入れられる楽器なんてないですけど、10人のうち3人か4人が賛同してくれるなら作る意味があると思います。それに、流行があとからついてくるパターンもたくさんあって、ローランドのCE-1なんてまさにそのパターン。1年半売れなかったのに、ハービー・ハンコックがキーボードに使っている写真が雑誌に出たのがきっかけで爆発的に売れたんです。もともとギタリスト向けに作ったのに(笑)。そういう風に、使い道をミュージシャンが見つけた時に真価が出てくることもありますよ。
- ありがとうございました。最後にファズを使っているギタリストに何かメッセージを。
- 梯
何のためにファズを使うのか、もしくは使おうとしているのか、それをもう一度考えてほしいなぁと思います。そして、演奏技法をクリエイトしてもらえると、楽器を作っている者としては嬉しいですね。
- エレクトリック・トランペットをマイルスが使い始めた当時はどう思いましたか?。
"自然だったね。フレイズとか、あんまり吹いていることは変わってないなと思った。1970年ごろにニューヨークのハーレムのバーでマイルスのライヴを観たんだけど、そのときのメンバーはチック・コリアやアイアート・モレイラで、ドラムはジャック・ディジョネットだった。俺の弟(日野元彦)も一緒に観に行ってたんだけど、弟はディジョネットがすごいって彼に狂って、弟と "あれだよな!そうだよな!" ってことになって(笑)。それで電気トランペットを俺もやり始めたわけ。そのころ大阪万博で僕のバンドがああいうエレクトリックのスタイルで演奏したら、ヨーロッパ・ジャズ・オールスターズで来日中だったダニエル・ユメールに "日野はマイルスの真似しているだけじゃないか" って言われたことがあるんだけどね。"